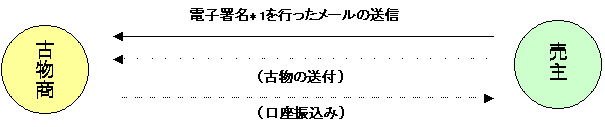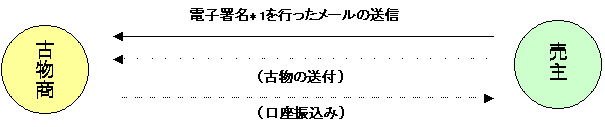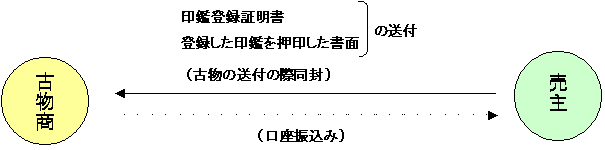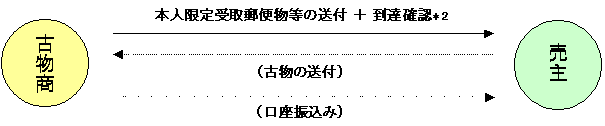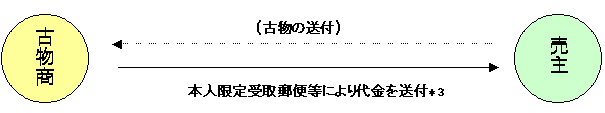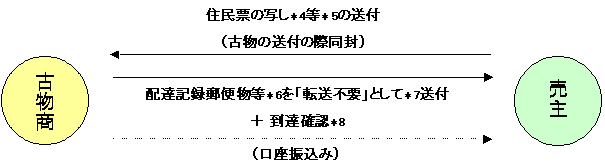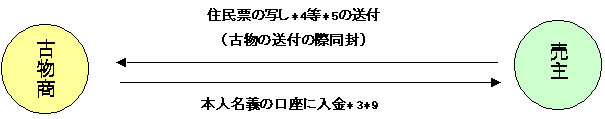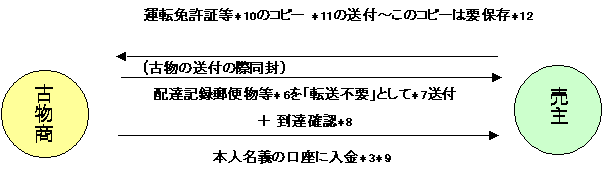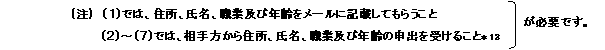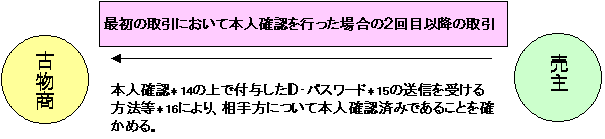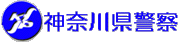下記の内容を最後まで読み了承される方は一番下の申込みから手続きして下さい
非対面取引における古物商の確認措置について
この度、古物営業法(昭和24年法律第108号)及び古物営業法施行規則(平成7年国家公安委員会規則第10号)が改正され、古物商が、インターネット等を利用して相手方と対面しなくても、古物の買受け等を行えるようにするため、そのような非対面取引において相手方の真偽を確認するための措置が規定されました。この改正は、平成15年4月1日から施行されました。
具体的な措置の内容は、以下のとおりですので、今後、非対面取引により古物の買受け等を行う場合には、これらの措置をとるようにしてください。
(1) 相手方から電子署名を行ったメールの送信を受けること。
(2) 相手方から印鑑登録証明書及び登録した印鑑を押印した書面の送付を受けること。
(3) 相手方に対して本人限定受取郵便物等を送付して、その到達を確かめること。
(4) 相手方に対して本人限定受取郵便等により古物の代金を送付する契約を結ぶこと。
(5) 相手方から住民票の写し等の送付を受け、そこに記載された住所あてに配達記録郵便物等を転送しない取扱いで送付して、その到達を確かめること。
(6) 相手方から住民票の写し等の送付を受け、そこに記載された本人の名義の預貯金口座等に古物の代金を入金する契約を結ぶこと。
(7) 相手方から身分証明書、運転免許証、国民健康保険被保険者証等のコピーの送付を受け、そこに記載された住所あてに配達記録郵便物等を転送しない取扱いで送付して、その到達を確かめ、あわせて、そのコピーに記載された本人の名義の預貯金口座等に古物の代金を入金する契約を結ぶこと(そのコピーを取引の記録とともに保存することとする)。
なお、相手方の真偽を確認するための措置を既にとっている者については、それ以降の取引の際に再度同様の措置をとる必要はなく、
(8) IDとパスワードの送信を受けること等により、相手方の真偽を確認するための措置を既にとっていることを確かめること。
で足りるものとします。
規則第15条第3項第7号
*1 「電子署名」は、認定(外国)認証事業者(電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第4条第1項又は第15条第1項の認定を受けた者)が証明するものでなければなりません。
*2 「到達確認」は、真偽の確認のための措置の一部をなすものであり、これを実施しなければ合法とはなりません。
「到達確認」の方法としては、以下のものがあります。
(ⅰ) 送付した本人限定受取郵便物等を古物と同封させて返送させる方法
(ⅱ) 本人限定受取郵便等により受付票等を送付し、当該受付票等を古物と同封させて返送させる方法
(ⅲ) 本人限定受取郵便物等に受付番号等を記載して送付し、当該受付番号等を相手方から電話、電子メール等により連絡させる方法
(ⅳ) 本人限定受取郵便等で往復葉書を送付し、その返信部を相手方から送付させる方法
(ⅴ) 本人限定受取郵便等で梱包材を送付し、その梱包材で梱包して古物を送付させる方法(古物商が送付した梱包材と相手方から送付を受けた古物の梱包材との同一性が判断できるように、自社専用で第三者が入手できない梱包材を使用する、梱包材に個別の番号を付しておくなどの措置が必要です。)
*3 古物商がこの方法により代金を支払うことを合意したにもかかわらず、実際にはその合意と異なる方法により代金を支払う場合には、改めて真偽の確認のための措置をとることが必要です。
*4 「住民票の写し」とは、市区町村が発行した原本のことであり、その原本をコピーしたものは含まれません。*7の「外国人登録原票の写し」も同様です。
*5 「住民票の写し等」の「等」とは、住民票の記載事項証明書、戸籍の謄本若しくは抄本(戸籍の附票の写しが添付されているものに限ります。)、印鑑登録証明書、外国人登録原票の写し又は外国人登録原票の記載事項証明書を指します。
*6 「配達記録郵便物等」の「等」には、書留郵便物及び小包郵便物が該当します。宅配便については、配達記録郵便と同様に、配達先の者から受領印をもらう等の取扱いをされるものでなければなりません。したがって、いわゆる宅配ボックスを利用する場合や、配達先の隣人に預けてその受領印をもらう場合は、これに含まれません。
*7 「転送不要」とするとは、差出人等が指定した送付先と異なる場所に送付する取扱いをされないように措置することです。郵便物については、その表面の見やすい所に「転送不要」と記載すれば足ります。
*8 「到達確認」は、真偽の確認のための措置の一部をなすものであり、これを実施しなければ合法とはなりません。
「到達確認」の方法としては、以下のものがあります。
(ⅰ) 送付した配達記録郵便物等を古物と同封させて返送させる方法
(ⅱ) 配達記録郵便等により受付票等を送付し、当該受付票等を古物と同封させて返送させる方法
(ⅲ) 配達記録郵便物等に受付番号等を記載して送付し、当該受付番号等を相手方から電話、電子メール等により連絡させる方法
(ⅳ) 配達記録郵便等で往復葉書を送付し、その返信部を相手方から送付させる方法
(ⅴ) 配達記録郵便等で梱包材を送付し、その梱包材で梱包して古物を送付させる方法(古物商が送付した梱包材と相手方から送付を受けた古物の梱包材との同一性が判断できるように、自社専用で第三者が入手できない梱包材を使用する、梱包材に個別の番号を付しておくなどの措置が必要です。)
*9 「口座に入金」とは、預貯金口座への振込み、郵便振替口座への払込み、これらの口座への振替を指します。
*10 「運転免許証等」とは、身分証明書、運転免許証、国民健康保険被保険者証等相手方の身元を確かめるに足りる資料を指します(古物営業法施行規則第15条第1項参照)。
*11 「コピー」には、デジタルカメラやスキャナによる画像や、これを印刷したものは含まれません。
*12 このコピーは、どの取引において送付を受けたかが分かるように保存しておかなければなりません。
*13 「相手方から住所、氏名、職業及び年齢の申出を受ける」方法は、特段制約がなく、電話、電子メール等任意のもので構いません。
*14 この場合の本人確認は、従来からの対面による措置(法第15条第1項第1号又は第2号)でも、(1)~(7)の措置でも構いません。
*15 「ID・パスワード」とは、不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成11年法律第128号)第2条第3項に規定する「識別符号」のことです。これは、(ⅰ)相手方ごとに違うもの(ID)であって、(ⅱ)その相手方以外に用いることができないようなもの(パスワード)であることが必要です。パスワードについては、連番になっている等容易に第三者が想像できるものは避け、英数字等を無作為に混在させたもの(u98kl2x、bdrgil0など)が望まれます。
なお、「ID」とはidentificationの略です。
*16 「ID・パスワードの送信を受ける方法等」の「等」とは、従来からの対面による措置(法第15条第1項第1号又は第2号)又は(1)~(7)の措置をとった者を識別でき、かつ、その者に第三者がなりすますことが困難な方法でなければなりません。
○ 古物営業法(昭和24年法律第108号)
第15条 古物商は、古物を買い受け、若しくは交換し、又は売却若しくは交換の委託を受けようとするときは、相手方の真偽を確認するため、次の各号のいずれかに掲げる措置をとらなければならない。
一・二 (略)
三 相手方からその住所、氏名、職業及び年齢の電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。以下同じ。)による記録であつて、これらの情報についてその者による電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいい、当該電子署名について同法第4条第1項又は第15条第1項の認定を受けた者により同法第2条第2項に規定する証明がされるものに限る。)が行われているものの提供を受けること。
四 (略)
第15条 (略)
2 (略)
3 法第15条第1項第4号の国家公安委員会規則で定める措置は、次のとおりとする。
一 相手方から、その住所、氏名、職業及び年齢の申出を受けるとともに、その印鑑登録証明書及び当該印鑑登録証明書に係る印鑑を押印した書面の送付を受けること。
二 相手方からその住所、氏名、職業及び年齢の申出を受け、並びにその者に対して、本人限定受取郵便物等(名あて人本人若しくは差出人の指定した名あて人に代わって受け取ることができる者に限り交付する取扱いをされる郵便物又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者が送達する同条第3項に規定する信書便物(以下「信書便物」という。)をいう。以下同じ。)を送付し、かつ、その到達を確かめること。
三 相手方からその住所、氏名、職業及び年齢の申出を受け、並びにその者に対して金品を内容とする本人限定受取郵便物等を送付する方法により当該古物の代金を支払うことを約すること。
四 相手方からその住所、氏名、職業及び年齢の申出を受けるとともにその住民票の写し、住民票の記載事項証明書、戸籍の謄本若しくは抄本(戸籍の附票の写しが添付されているものに限る。)、印鑑登録証明書、外国人登録原票の写し又は外国人登録原票の記載事項証明書(以下「住民票の写し等」という。)の送付を受け、並びに当該住民票の写し等に記載されたその者の住所にあてて配達記録郵便物等(引受け及び配達の記録をする取扱いをされる郵便物若しくは信書便物又はこれと同様の取扱いをされる貨物(貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第3条の許可を受けた者その他の適法に貨物の運送の事業を行う者が運送するものに限る。)をいう。以下同じ。)で転送をしない取扱いをされるものを送付し、かつ、その到達を確かめること。
五 相手方からその住所、氏名、職業及び年齢の申出を受けるとともにその住民票の写し等の送付を受け、並びに当該住民票の写し等に記載されたその者の氏名を名義人の氏名とする預貯金口座への振込み若しくは郵便振替口座への払込み又はこれらの口座への振替の方法により当該古物の代金を支払うことを約すること。
六 相手方からその住所、氏名、職業及び年齢の申出を受けるとともにその身分証明書、運転免許証、国民健康保険被保険者証等その者の身元を確かめるに足りる資料の写し(明瞭に表示されたものに限る。)の送付を受け、当該資料の写しに記載されたその者の住所にあてて配達記録郵便物等で転送をしない取扱いをされるものを送付し、かつ、その到達を確かめ、並びに当該資料の写しに記載されたその者の氏名を名義人の氏名とする預貯金口座への振込み若しくは郵便振替口座への払込み又はこれらの口座への振替の方法により当該古物の代金を支払うことを約すること(当該古物に係る法第16条の帳簿等又は電磁的方法による記録とともに当該資料の写しを保存する場合に限る。)。
七 法第15条第1項第1号から第3号まで又は前各号に掲げる措置をとった者に対し識別符号(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成11年法律第128号)第2条第3項に規定する識別符号をいう。)を付し、その送信を受けることその他のこれらの規定に掲げる措置をとった者を識別でき、かつ、その者に第三者がなりすますことが困難な方法により、相手方についてこれらの規定に掲げる措置を既にとっていることを確かめること。
4 (略)
参照
警視庁
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/
東京都公安委員会
http://www.kouaniinkai.metro.tokyo.jp/index.html
調布警察
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/8/chofu/
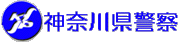
古物商のホームページを利用した取引に関する規定の整備について
http://www.police.pref.kanagawa.jp/mes/mesd0045.htm
古物商とは
リサイクルショップや質屋等、中古品(古物)を扱う商売を行うには、公安委員会での『古物商』の営業許可(古物商許可証)が必要となります。
この許可(資格ではない)制は、盗難品の流通経路として中古市場が利用される恐れがある為に、古物営業法によって定められている規定なのですが、もし、これを知らずに無許可で中古品を扱うビジネスを行った場合には、「3年以下の懲役、又は100万円以下の罰金」というかなり厳しい処罰があります。
では、どの程度の事を行うと許可が必要になるのか、という事なのですが、個人が、自分の所有物を処分する目的で、フリーマーケットやネットオークションを利用する場合には、『古物商』許可は必要ありません。
但し、他人から物品を買取り、もしくは委託によって営利を目的としてネットオ-クションに出品したり、フリーマーケットで販売を行う中古品の売買については、ほとんどの場合がこの『古物商』に該当します。
又、出品者が個人であっても、公序良俗に反したり、違法性のある物を出品した場合は、摘発の対象になるケースもあります。
●古物とは、
①一度使用された物品
②使用されない物品で使用のために取引されたもの
③これらいずれかの物品に「幾分の手入れ」をしたものをいいます。
ここでいう「使用」とは、その物本来の目的にしたがってこれを「使う」事をいいます。また、「幾分の手入れ」とは、物の本来の性質、用途に変化を及ぼさない形で、修理等を行うことをいいます。
●古物商とは、
許可を受けて、古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、交換する営業の事。
●古物商の区分とは、
①美術品類 書画、彫刻、工芸品等
②衣類 和服類、洋服類、その他の衣料品
③時計・宝飾品類 時計、眼鏡、宝石類、装身具類、貴金属類等
④自動車 その部分品を含みます。
⑤自動二輪車及び原動機付自転車 これらの部分品を含みます。
⑥自転車類 その部分品を含みます。
⑦写真機類 写真機、光学器等
⑧事務機器類 レジスター、タイプライター、計算機、謄写機、ワードプロセッサー、ファクシミリ装置、事務用電子計算機等
⑨機械工具類 電機類、工作機械、土木機械、化学機械、工具等
⑩道具類 家具、じゅう器、運動用具類、楽器、磁気記録媒体、蓄音機用レコード、磁気的方法又は光学的方法により音、影像又はプログラムを記録した物等
⑪皮革・ゴム製品類 カバン、靴等
⑫書籍
⑬金券類 商品券、乗車券、郵便切手及びこれらに類する証票その他の物として古物営業法施行令第1条に定められているもの
『古物商』は上記の13区分に分かれており、自分が扱おうとする商品の区分を申請書に明記して、それ以外の区分の商品を扱う場合には再度、区分変更の届け出を行う必要あり。(同時に複数の区分を登録する事は可能。)
非対面取引における古物商の確認措置の内容を了解し申込む
*お問い合わせ内容の欄に販売又は購入とお書きください
以前ご利用頂いた方にはMailにてID・パスワードをお送りいたしましたので
ユーザーからID・パスワードを入力してお入りください